「平井たかまさ」は、以下3つの政策を力強く進めて参ります。
- 東日本大震災からの「真の復興」
- 「いわきのIT改革」で防災、行政の改善、教育改革
- 「脱原発」と力強い地方創生

東日本大震災からの「真の復興」
2万人あまりの尊い生命を犠牲にした東日本大震災が発生してから、早いもので9年の月日が経ちました。しかしいまだ被災3県では5万人近い方々が避難生活を強いられており、復興に向けてやらなければならない事はまだまだ山積しております。さらに昨年の台風19号や新型コロナウィルス感染症による被害の拡大が続いており、まさに待ったなしの状況です。
真の復興とは、元に状態に戻す「復旧」ではありません。
元に戻すという事だけでも、とてつもなく大変な事ではあります。しかし元に戻す大きな力があるのであれば、さらにその先の「進化」まで進める事が出来るはずです。
そこまで行き着く事で、はじめて「真の復興」と言えるのではないでしょうか。

「いわきのIT改革」で防災、行政の改善、教育改革
ITの力を最大限活用し、感染症や災害に強い都市の構築、行政の改善、教育の改革を目指します。
「スピーディーで、具体的な情報を共有する」システムを構築
感染症や津波、川の氾濫、土砂崩れ等の情報を、住民の皆様へ「スピーディーで、具体的な情報を共有する」システムを構築する必要があります。
この情報共有システムにより、市民の皆様の安心感、そして最も大切な「命」を守る事が出来ます。
昨年台風19号により犯艦した夏井川の復興ボランテイアに参加させていただいた際、被災された方は無事でしたが、不幸にもペットのわんちゃんが溺死してしまい、大変悲しんでおられました。
大量の水に気付いた時は、既にご自宅の前まで水が迫ってきており、人の避難だけで精一杯だったのです。また、不幸にも同災害によりいわき市内で合計12名の死者が出てしまっています。
川の氾濫の前兆を確認出来た時点でアラートを出していれば、この尊い命は救えた可能性が非常に高いと思います。
優先度の高い情報通知の際は、スマートフォンによるポップアップアラート、サイレン用スピーカー双方による同時情報通知を想定していますが、いわきはサイレン用スピーカーが非常に少なく、早急に各地域へ設置する必要があるという課題もあります。
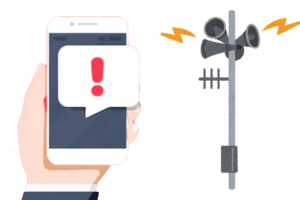
また、情報共有システムの構築により、新型コロナウィルスの被害を受けている外食店様等への支援の一環として、例えばテイクアウトサービス等の情報の共有(この場合はスマホのポップアップのみ)にも、活用出来ます。
人工知能(AI)の力で、「想定外」を「想定内」に
どういったリスクがあるか普段から分析し、リスクに備えておく事も重要です。
コロナウィルス感染症や台風19号、東日本大震災の際に頻発してしまった「想定外」を、AIの分析力でリスクを顕在化し「想定内にする」事が可能です。
また、各リスクを顕在化し数値化する事で、
「税金をより効果的に使う事が出来る」と考えております。
利用価値の低いハコモノに、莫大な税金を使ってはいないでしょうか?
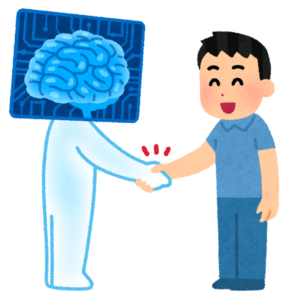
これからは、いかに「AIをうまく活用出来るか」が重要です。
各種申請手続きの「簡素化」
コロナ渦に伴う「特別定額給付金」や台風19号に伴う各種助成金等をはじめとした各種申請手続きが現状非常に複雑でわかり難く、非効率です。
結果、今すぐ支援が必要な方へ、必要なお金や物資を届ける事が出来ていません。
既に、地方自治体主導で、デジタル化等による手続きの簡素化が進められており、いわき市も福島県と連携して、こうした取り組みを進めるべきです。
参考:内閣府「地方自治体における行政手続簡素化 事例集(令和元年6月時点)」
その他、教育のオンライン化やテレワークの推進、お年寄りの皆様が安心して免許証を返納出来るような自動運転(Lv4、5)の導入や移動手段の改革 MaaSによる地域活性化、家に居ながら治療が受けれる遠隔医療の普及。
これらを「いわきのIT改革」として、あわせて力強く推進して参ります。
強いものだけが生き残る世の中から、みんなが安心して暮らせる街を、ITの力を活用し、実現したいと考えています。
欧米の合理的な経営ではなし得ない、日本の「地域に根付いた伝統・継続性を重視した中小企業の底力」をITの力をうまく活用し、皆様の生活を豊に、笑顔のある街にしたいと強く考えています。

「脱原発」と力強い地方創生
段階的に脱原発依存を進め、将来的には原発に依存しない社会を目指します。

お願い
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
下記ページもご覧頂けると幸いです。
お問い合わせは、こちらからお願い致します。
日々の活動内容や近況はFacebookへ投稿しています。
是非、友達登録をお願い致します。





